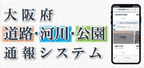長野公園新聞 2014春号(長野公園新聞記事内容ご紹介)
- 2014年 6月20日(金) 15:36 JST

さくらまつりを行います!(終了しました)
2月の大雪を経て、寒い日々と暖かい日々が続いております。まさに『三寒四温』といったところですね。奥河内さくら公園(長野地区)や奥河内あじさい公園(河合寺地区)、奥河内天野キャンプの森(天野山地区)のウメが咲き始め、サクラもつぼみが膨らみ始めております。
さて、春を目前に控え、サクラの時期がやってまいります。長野公園では、このサクラを皆さんに存分に楽しんでいただくために、今年も「夜桜ライトアップ」を実施いたします。奥河内さくら公園(長野地区)は新河内長野八景のひとつにも選ばれる、河内長野市内の夜桜の名所とされています。その名所の名に恥じぬよう、3月29日(土)~4月13日(日)の2週間ほど、長野公園の夜桜をライトアップいたします。また、4月5日(土)には、花見を存分に楽しんでいただくために、地域の団体と連携して実施する花見イベント『奥河内meets SAKURA』も企画されておりますので、みなさん、ぜひ足をお運びいただきますよう、よろしくお願いいたします。

春の長野公園でみられる植物

サクラ:奥河内さくら公園(長野地区)緑の広場など

ウメ:奥河内あじさい公園(河合寺地区)展望台など

ヒラドツツジ:奥河内さくら公園(長野地区)など
ながのこうえん最新情報
公園観察ガイド(参加費無料)
緑あふれる長野公園には昆虫や鳥類など様々な生き物が生息しており、自然散策や夏休みの自由研究にはもってこいのフィールドです。そして、長野公園では昆虫の専門家である生き物好きのスタッフによる公園観察ガイドを実施しています。

「これはどんな虫、生き物?」と思った方、長野公園の自然を知りたい方、お気軽にご連絡ください。
都市公園長野公園管理共同体 長野公園管理事務所
河内長野市末広町581-1
TEL:0721-62-2772 FAX:0721-62-2810
時間:9:00~17:00(観察ガイドはスタッフ在駐時のみ) 駐車場:なし
料金:無料 休み:なし 予約:事前申し込み要(1週間前まで)
長野公園で見られる生き物たち
ジョウビタキ(Phoenicurus auroreus)
全長15cm前後のヒタキ類。全国に冬鳥として飛来するが、北海道では繁殖例がある。オスは頭部が灰色、顔が黒色、胸腹部にかけてオレンジ色。メスは全体的に灰褐色で地味な色合いだが、雌雄ともに翼に白斑がある。農耕地や林縁部など開けた場所に多く、公園や人家の庭でもよく見られる。雑食性で昆虫や果実などを食べる。木や枝の上によく止まり、「ヒッヒッ カッカッカ」と鳴く。長野公園では主に冬に見られる。奥河内さくら公園(長野地区)や奥河内あじさい公園(河合寺地区)では広場によく出現し、姿は見えなくても声を聞くことができる。

オス

メス
長野公園の巣箱と巣箱を利用する生き物たち
自然豊かな長野公園では生き物たちを身近に観察できる空間づくりの一環として鳥の巣箱を設置しています。先日、河内長野市との共同のイベントで巣箱の清掃を兼ねた観察会を行いました。今回はここ長野公園に設置している巣箱とそれを利用する生き物について紹介したいと思います。
長野公園では河内長野野鳥の会の協力を得て、過去に奥河内楠公の里(丸山地区)に鳥の巣箱を設置したことがあります。それからしばらく設置していませんでしたが、昨年度から再び河内長野野鳥の会の方の協力を得て、奥河内さくら公園(長野地区)に設置しています。巣箱は入口の径の大きさや形状によって入る種類がだいたい決まっています。



現在、長野公園に設置している巣箱はシジュウカラとムクドリ用の巣箱で園内各所の10数ヶ所に設置しています。イベントではこれらの巣箱を取り外して、中身をきれいに掃除して再びかけなおす作業で、5人の子供たちが参加してくれました。みんなで事務所近くに設置しているシジュウカラ用の巣箱を探して清掃しました。清掃できた巣箱は全部で5つ。その中で巣材があったのは2つでした。さらに2つのうち産卵していたと思われるのは1つでした。講師の先生によるとシジュウカラが産卵している巣材の産座は獣毛など毛状のものを敷き詰めてあるそうで、最初に見つけた巣にはその産座がありませんでした。でも、ちゃんと産卵してくれていてほっとしました。
一方、気になるのは巣材が入っていなかった巣箱。実は全くの空っぽというわけではありませんでした。中にはキアシナガバチやハリブトシリアゲアリ、ヨコヅナサシガメの幼虫、ヒメクロゴキブリの幼虫、ニホンヤモリ、クモやダニの仲間が入っていました。これらの生き物は寒い冬の間、越冬する場所として鳥の巣箱を利用していると考えられます。
また、鳥の巣材の中にも鳥に寄生したり、寝床としてや巣材を食べたりする生き物などが生息しており、鳥の巣という場所が一つの生態系になっていることもあります。このように鳥の巣を中心として多くの生き物が関わりあいを身近に観察できることが巣箱の魅力だと思います。これからも長野公園で巣箱づくりや観察会を行っていくなど巣箱の魅力を伝えていけたらと思います。
とぴっくす:昆虫採集のすゝめ③
昆虫は他の生き物に比べると種類が多く、近縁種なども多いため正確に種を同定するためには標本を残すことが重要になってきます。そこで今回から昆虫標本の作製について紹介していきたいと思います。まず標本作成を行うにあたり、必要な道具を紹介していきたいと思います。
- ①昆虫針(図1):長さ約4cmの金属製の針で昆虫の乾燥標本を作るうえでの必須アイテムです。玉状の有頭針と無頭針があります。刺す昆虫の大きさによって太さが違い、細い00号から太い6号まであります。家にある針を利用するのではなく、必ず市販で専用の針を購入してください。
- ②玉針(図2):昆虫針と違って直接虫体に刺すのではなく昆虫を固定するために使います。家にあるもので代用可能です。
- ③展翅板(図3):チョウ・ガ類、トンボ、ハチ、アブなど翅を広げて展翅するために使う板です。昆虫針と同様に大きさが虫によって違います。自分で作成することも可能ですが、市販の物を購入した方がよいでしょう。
- ④展翅テープ(図4):展翅板に載せて翅を固定するために使います。展翅板や翅の大きさに合わせて使い分けましょう。
- ⑤展足板(図5):昆虫の体を固定する板です。市販の物がありますが、発泡スチロールで代用可能です。
- ⑥柄付き針(図6):昆虫の翅や脚をそろえたりするのに便利です。つまようじや割りばしの先に昆虫針をつけることで代用する事も可能です。
- ⑦ピンセット(図7):柄付き針と同様に翅や脚をそろえたり、虫を掴んだりするのに便利です。
- ⑧平均台(図8):標本の高さをそろえるために必要です。
- ⑨ラベル(図9):昆虫の名前や採集場所、採集者名など標本の情報を載せるために必須です。
- ⑩標本箱(図10):標本を保管するために必要です。大きさによっては少し高価ですが、重要なアイテムです。
- ⑪その他:捕まえた虫を殺す酢酸エチルやアルコール、チョウやトンボなどを捕まえた時に入れる三角紙などがあります。

昆虫針(図1)

玉針(図2)

展翅板(図3)

展翅テープ(図4)

展足板(図5)

柄付き針(図6)

ピンセット(図7)

平均台(図8)
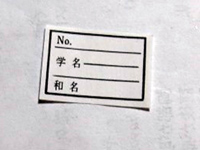
ラベル(図9)

標本箱(図10)