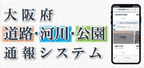長野公園新聞 冬号(長野公園新聞記事内容ご紹介)
- 2013年12月21日(土) 21:43 JST

長野公園では、落葉樹の樹々から葉が落ち、最も冷え込む冬が到来しました公園内では、植物たちも冬支度を始めており、ナンテンの実が真っ赤に色づき、サザンカが開花し始め、スイセンも開花の準備を始めております。冬場は見どころがめっきり少なくなりますが、それでも植物たちは粛々と花や実をつけ、私たちを楽しませてくれます。
また、落葉樹の樹々から葉が落ちるため、野生の鳥たちの姿を観察しやすくなります。ノスリやセグロセキレイ、運が良ければ、長野地区の展望台のはるか上を横切るオオタカを見ることができます。双眼鏡を片手に、自然の鳥たちを見に来ることもおすすめです。
野鳥だけでなく、昆虫たちも越冬の準備を始めます。日本の国蝶であるオオムラサキは、落葉樹であるエノキの落ち葉を利用して幼虫のまま冬を越し、来年、その美しい姿を私たちの前に表してくれる準備をしてくれています。
長野公園の豊かな自然環境は、冬でも皆さんを楽しませてくれるとおもいます。寒い中でも、園内の小さな息吹を感じに、長野公園に遊びに来てはいかがでしょうか?
冬の長野公園でみられる植物

サザンカ:奥河内あじさい公園(河合寺地区)展望台など

ナンテン:奥河内さくら公園(長野地区)事務所附近など

スイセン:奥河内あじさい公園(河合寺地区)桜広場など
長野公園掲示板
公園観察ガイド(参加費無料)
緑あふれる長野公園には昆虫や鳥類など様々な生き物が生息しており、自然散策や夏休みの自由研究にはもってこいのフィールドです。そして、長野公園では昆虫の専門家である生き物好きのスタッフによる公園観察ガイドを実施しています。

「これはどんな虫、生き物?」と思った方、長野公園の自然を知りたい方、お気軽にご連絡ください。
都市公園長野公園管理共同体 長野公園管理事務所
河内長野市末広町581-1
TEL:0721-62-2772 FAX:0721-62-2810
時間:9:00~17:00(観察ガイドはスタッフ在駐時のみ) 駐車場:なし
料金:無料 休み:なし 予約:事前申し込み要(1週間前まで)
長野公園で見られる生き物たち
Vol.01ノスリ (Buteo japonicas)
全長50~60cm、翼開長120~140cmでやや大型のタカ類。北海道~九州に留鳥または冬鳥として生息する。全体的に褐色で腹部や翼の内側は白色が目立つ。平地から山地周辺の農耕地など開けた場所で多く見られ、ネズミやカエルなどを捕えて食べる。大阪府レッドデータブックでは要注目種として記載されている。写真は河内長野市内で撮影したもの。長野公園では冬に見られ、奥河内さくら公園(長野地区)や奥河内あじさい公園(河合寺地区)の展望台から上空を飛んでいる姿をたまに見ることができる。
長野公園最新情報
長野公園奥河内さくら公園(長野地区)の緑の広場には、八角形の花壇があるのをご存知でしょうか?この花壇、新年を迎える雰囲気作りのために、12月のこの時期に葉牡丹が植えられます。葉牡丹はアブラナ科の多年草で、園芸植物として鮮やかな葉を鑑賞されています。名前の由来は、葉を牡丹の花に見立てたもので、耐寒性に優れ、冬の公園を彩るほか、門松の添え物にも利用されます。
長野公園に植えられている葉牡丹は、河内長野の花農家さんが育ててくれた、大きさも見事な葉牡丹です。皆さん、ぜひ見に来てください。
秋のやわらかい日差しに照らされている見事なモミジの紅葉を楽しみに、奥河内もみじ公園(延命寺地区)に来てみませんか?

緑の広場の八画花壇(写真は昨年の花壇)
とぴっくす「昆虫採集のすゝめ②」
今回は昆虫採集について紹介していきたいと思います。昆虫採集とは言葉どおり、研究や個人的なコレクションとして昆虫を捕まえることです。そして、採集するには方法を詳しく知っておく必要があります。ふつう昆虫採集と聞くと網を振って捕まえるイメージがありますが、様々な方法があります。今回はその中でも代表的な採集法を紹介します。
- 見採り法(ルッキング採集)・・・昆虫採集の基本中の基本で昆虫がいそうな場所で虫網を持って歩き回る方法です。虫網がなくても石をどかしてみたり、樹皮をめくったりするなど誰にでもできる方法です。特定の昆虫を採集する場合はその昆虫の習性を理解しておくと効率があがります。
- 叩き網法(ビーティング採集)・・・木の枝などの下に虫網をおいて、木の枝を叩いたり揺らしたりして落ちてくる昆虫を採集する方法です。虫網がなくてもビニール傘などでできます。小型の昆虫を捕まえるのに便利です。
- すくい採り(スイーピング採集)・・・見採り中によく使う方法で、虫網を使って草むらなどをすくいながら採集する方法です。バッタなど草むらに隠れている昆虫を採集するのに向いています。
- 街灯採集・・・夜、光に集まる昆虫を採集する方法です。電灯や自動販売機などに集まってくる昆虫を採集します。大型のガやカブトムシの仲間など様々な昆虫が採集できます。注意点として不審者に間違われないようにしましょう。
- 土壌篩い・・・スコップで土をすくって、台所用の金網で白色バットの上などに篩い落として採集する方法です。アリやトビムシなど微小な昆虫類を採集するのに向いています。

すくい採り(スイーピング採集)

叩き網法(ビーティング採集)

叩き網法(ビーティング採集)
以上が代表的な昆虫採集の方法です。他にも餌を使って捕えるトラップや水生昆虫を捕まえる方法など様々な方法がありますが、種類によって様々なので興味がある方はぜひご自分で調べてみて下さい。次回は昆虫の標本作成についてご紹介したいと思います。
長野公園で越冬する昆虫

オオムラサキの幼虫

チビクワガタの成虫

朽木とキセルガイ
今回はここ長野公園で越冬する昆虫を紹介したいと思います。越冬とは、冬になると気温が下がり、餌がなくなると活動や成長を止めてじっとしている状態のことです(休眠)。昆虫って冬も見られるの?と聞かれることがよくありますが、目をこらして探してみると色々な場所で越冬している昆虫を見ることができます。どのような場所で越冬しているか昆虫の種類によって様々です。
では、ここ長野公園ではどんな場所でどんな昆虫が越冬しているか見てきました。私たちは河合寺地区内でとある昆虫を探してみることにしました。それは日本の国蝶であるオオムラサキです。オオムラサキは大型のタテハチョウで幼虫はエノキの葉を食べ、成虫はクヌギの樹液などを吸汁して生活しています。夏の風物詩でもあるカブトムシやクワガタと同じく雑木林の代表的存在ですが、近年雑木林の減少や食樹であるエノキが手入れされなくなったりしたことから減少し、環境省・大阪府ともに準絶滅危惧種に指定されています。長野公園でも数は減っていますが、初夏~夏にかけて河合寺地区や丸山地区で優雅に飛ぶ姿を見ることができます。オオムラサキは幼虫で越冬し、冬になると食樹のエノキから降りて周辺の落ち葉の下で越冬し、春になり新芽が芽吹くと再び木に登ります。この習性を利用してエノキ周辺の落ち葉を探してみることにしました。
風が冷たい中、落ち葉をかき分け幼虫を探す私と所長。最初のポイントでは収穫ゼロで移動して展望台近くの大きなエノキに向かいました。1頭は見つけたいと願いながら探し続け、探すこと約1時間、ついにエノキの葉裏で越冬しているオオムラサキの幼虫を見つけました。結局、収穫は見つけた1頭だけでしたが、他にも見逃していたかもしれません。
その後、オオムラサキ以外の昆虫を見つけるために展望台周辺に転がっている朽木を掘りました。朽木には多くの昆虫が越冬していることが知られています。朽木を割ると、チビクワガタの成虫やオバボタルの幼虫、オオハリアリなどの昆虫が越冬しており、キセルガイやカタツムリ、ムカデやクモなど昆虫以外にもたくさんの生き物が越冬していました。このように冬場でも探し回れば色々な生き物に出会うことができます。
今回のような朽木や落ち葉以外では、樹上に重なった葉っぱの隠れ家であるリーフシェルター、枝や樹皮の下、土中や石の下、人家なども昆虫の越冬場所として利用されています。ぜひ皆さんも身近な場所で越冬している昆虫たちを探してみてはいかがでしょうか。