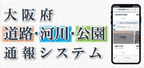長野公園新聞 2017冬号(長野公園新聞記事内容ご紹介)
- 2018年 1月10日(水) 11:04 JST
日に日に寒波が強まり、いよいよ冬本番。皆さま、ご体調はいかがでしょうか。インフルエンザの流行が始まりましたね。この寒さも相まって暖を取りたいところですが、暖房などによる空気の乾燥は喉の痛みのほか、ウイルスを活発化させてしまうので注意が必要です。外出時はマスクを着用し、ご帰宅の際は手洗いうがいを心がけてください。
さて、秋号の冒頭でこの季節の楽しみとして奥河内もみじ公園(延命寺地区)のモミジを紹介しましたが、毎年11月上旬から下旬にかけてモミジが見どころを迎え、賑わいを増しますが、今年はある問題が・・・。実は10月下旬に各地で大きな被害をもたらした台風21号の影響を受け、当地区園内でも土砂崩れが発生いたしました。安全確保のため現在も園内の一部が通行不可の状態が続いています。そのためお越しの際には迂回して頂くなど対応をさせていただいており、大変ご不便をおかけしております。
なお、立ち入り禁止箇所や迂回路などについては当公園ホームページや園内各所に掲示しておりますので、そちらをご覧ください。復旧には当分時間がかかるかもしれませんが、園内の散策は十分可能ですのでぜひお立ち寄りください。
一方、季節を感じさせる生き物として冬鳥が園内に出没するようになりました。代表的な冬鳥であるジョウビタキやシロハラなどが園内各所に飛来しています。これから寒さが強まる季節、体を温める運動がてらにバードウオッチングをしてみてはいかがでしょうか。

冬でも見られる オツネントンボ

越冬場所を探す ニホンヒキガエル

冬の野鳥 ジョウビタキ
長野公園で見られる生き物

ルリタテハ Kaniska canace
開長45mm前後の中型のタテハチョウ。国内では北海道南部~南西諸島にかけて広く分布し、平地から山地の森林や林縁部に生息するほか、公園などの緑地にも飛来する。翅は表面が青みのある黒色を基調に名前の由来にもなっている瑠璃色の帯が入るのが特徴。
一方、裏面は地味な灰褐色。成虫は暖地では年2~3回発生し、主に5~6月の初夏と10~11月の晩秋に発生する。冬季は成虫で越冬し、暖かい日には真冬でも日向ぼっこする姿を見ることができる。幼虫はサルトリイバラやホトトギスなどを食べる。成虫は花にはほとんど訪花せず、樹液など好むほか動物の糞などにも集まる。
長野公園では全地区で生息を確認し、園内では発生時期に姿を見ることができる。写真は奥河内楠公の郷(丸山地区)で撮影した個体。木の上など高い場所に止まり、縄張りを張る。
冬鳥を見つけよう!!
冒頭でもご紹介したように園内各所に冬鳥が飛来する季節になりました。冬鳥は渡り鳥の一種で秋から冬にかけてロシアや北日本など寒い北の地域から越冬のために暖かい南の地域に渡ってくる鳥のことです。代表的な種類としてツグミやジョウビタキ、カモ類やカモメ類などがあげられます。一方、反対に日本で繁殖するために渡ってくるのが夏鳥で、ツバメやオオルリ、サシバなどがいます。今回はここ長野公園で見られる冬鳥について紹介したいと思います。
冬鳥と聞いて私がまず思い浮かべるのが、ジョウビタキです。本種はスズメよりほんの少し小さな小鳥でオスは腹部が鮮やかなオレンジ色をしています。最も身近な冬鳥で、庭先や公園など人が多い場所でも普通に見ることができ、冬の園内で見かける鳥の代表格でもあります。そのためいつ飛来したのかを知ることでその年の冬の自然環境を示す指標にもなっています。昔は冬鳥でしたが、近年は日本で繁殖することもあるそうです。
続いてツグミ。本種はムクドリと似たような大きさでジョウビタキと並んで身近な冬鳥であり、園内の広場で地面をつつきながら歩いている姿をよく見かけます。今は法律で禁止されていますが、食べると美味しいらしいですよ。

ジョウビタキ(オス)

ツグミ

アトリ

ウソ
代表的な上記2種の冬鳥以外にも多くの野鳥が園内に飛来します。まれにしか見ることができないレアな野鳥もいるかもしれません。これからの季節、バードウオッチングがお勧めです!!
擬態について
みなさんは「擬態」というものについてご存知でしょうか? 擬態 Mimicryとは生物とくに動物が、身を守るためや獲物を捕らえるために姿を別のものに姿を似せることを指します。擬態といっても以下のような様々な種類があり、生物によってそれぞれ工夫を凝らしています。
隠ぺい擬態
ある生き物が捕食者などから身を守るために周辺の植物や環境に自身の体や体色を似せること。 例:バッタ、ナナフシなど

トゲナナフシ・・・落ち葉や枯れ枝に擬態して身を守る。
攻撃擬態
捕食者が獲物に気づかれないように周辺の植物や環境に自身の体や体色を似せること。 例:カマキリなど

オオカマキリ・・・自身の体色を周辺の環境に合わせることで獲物を捕りやすくする。
ベイツ型擬態
毒を持つ生物や危険な生物をモデルに毒のない生き物がその生物に姿を似せること。 例:ツマグロヒョウモン、ハチモドキハナアブなど

オオカマキリ・・・自身の体色を周辺の環境に合わせることで獲物を捕りやすくする。
ミューラー型擬態
毒を持つ生物が同じく毒を持つ生物と互いに似せあっていること。 例:スズメバチ、アシナガバチなど

スズメバチ類・・・スズメバチやアシナガバチの仲間はだいたいよく似た姿をしており、互いに似せあうことで有毒であることを捕食者などの敵にアピールしている。