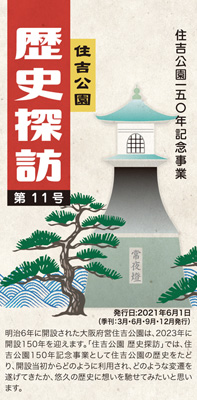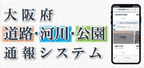まちの公園新聞 2021なつ号(まちの公園新聞記事内容ご紹介)
- 2021年 6月13日(日) 16:01 JST
器材付きで楽々‼ 有料BBQエリアを開設
桜広場に、有料で機材、食材等を提供し「手ぶらでバーベキュー」ができるエリアを設けました。
3密を避けながら、手ぶらで気軽にバーベキューを楽しんでください。
事前予約が必要です。予約総合受付 TEL(06)7890-7474
- 開設期間:6月1日~11月30日
- 利用時間:2部制(有料、時間延長可)
①10時~13時 ②15時~18時
※新型コロナウィルス感染予防対策への取り組みにご協力ください。
※大阪府「緊急事態宣言」のため、営業を中断しておりますが、再開時は公園ホームページなどでご案内いたします。